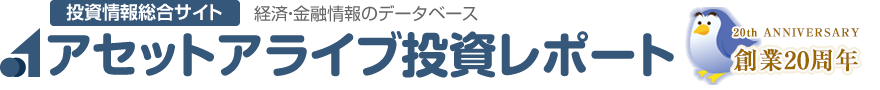2014年4月1日、消費税率が5%から8%に上がった。2014年度の税収は約5兆円増加する見込み。2.9兆円を基礎年金の国庫負担に、1.3兆円を社会保障費に、5000億円を子育て支援に充当する。
消費増税の影響を避けるため、政府は5.5兆円の経済対策を決定。公共事業中心の防災・減災対策で1.2兆円、低所得層への現金給付で3400億円などを計上。当対策で実質GDPを1%程度押し上げ、25万人の雇用を生み出すと試算している。
また、2015年10月に予定されている消費税率の10%への引き上げは、8%に引き上げた後の需要の落ち込みを念頭に「2014年7-9月期に今の流れを取り戻せるか」に注目し、経済指標を勘案して決断するとしている。
{財政健全化}
日本の公的債務の対GDP比は214%と借入金が積み上がり財政が悪化している。日本政府は2015年度までに国と地方の基礎的財政収支(プライマリーバランス)の赤字の名目GDP比を2010年度から半減し、2020年度までに黒字化する目標を掲げている。
内閣府の試算によると、2015年度にプライマリーバランスの赤字を名目GDP比で半減させるためには2度の消費増税に加えて、2014年、2015年に少なくとも5兆円の税収増加か歳出削減が必要になるという。増収増だけで対応する場合は、名目経済成長率を3%近くまで伸ばさなければならない。
{GDPへの影響}
内閣府は消費税1%の引き上げでGDPが約0.3ポイント、300億ドル(約3兆円)減少すると試算している。2014年4月の5%から8%への引き上げ時にはGDPが約0.9ポイント、900億ドル(約9兆円)減、2015年10月の8%から10%への引き上げ時にはGDPが約0.6ポイント、600億ドル(約6兆円)の減少が見込まれる。
| 時期 |
増税 |
GDP |
影響額 |
| 2014年4月 |
5%→8% |
▲0.9ポイント |
▲900億ドル(▲約9兆円) |
| 2015年10月 |
8%→10% |
▲0.6ポイント |
▲600億ドル(▲約6兆円) |
| 2014~2015年 |
5%→10% |
▲1.5ポイント |
▲1500億ドル(▲約15兆円) |
【実質GDP成長率】
政府は、2014年7月22日、2014年度の実質GDP成長率を1.4%から1.2%に下方修正した。消費増税に伴う駆け込み需要と反動減が想定より大きかった。2015年度は1.4%と予測。個人消費や設備投資など民間需要が伸び、1%未満とされる潜在成長率を上回る見通し。
|
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
| 実質GDP成長率 |
1.4% |
1.5% |
1.4%→1.2% |
1.4% |
【2014年度GDP推移】
1-3月期の実質GDP成長率は1.6%増。個人消費は消費税増税前の駆け込み需要で好調。設備投資は景気回復の持続や企業収益の改善で上向いた。
【日銀発表の日本のGDP見通し】
|
2014年 |
2015年 |
| GDP見通し |
1.4%→1.3% |
1.6%→1.5% |
【世界機関による日本のGDP見通し】
|
2014年 |
| IMF |
1.4% |
| 世界銀行 |
1.4% |
| OECD |
1.2% |
{消費増税に伴う経済対策}
2013年12月5日、5.5兆円の経済対策を決めた。公共事業中心の防災・減災対策で1.2兆円、低所得層への現金給付で3400億円などを計上。政府は当対策で実質GDPを1%程度押し上げ、25万人の雇用を生むと試算している。
| 分野 |
内容 |
金額 |
| 震災復興事業 |
被災地のインフラ復旧 |
1.1兆円 |
| 福島の避難住民帰還支援 |
| 被災者向け現金給付 |
| 経済対策 |
老朽インフラ整備など防災・減災対策、原発事故対策 |
1.2兆円 |
| 農業の大規模化や農産物輸出促進策 |
2000億円 |
| 国産ロケットなど重点課題の研究開発 |
1600億円 |
| 東京五輪向け交通・物流整備 |
800億円 |
| 暮らし |
低所得者に現金給付 |
3400億円 |
| 子育て世帯に子供1人あたり1万円の現金給付 |
1500億円 |
| 住宅購入者に最大30万円の現金給付 |
1600億円 |
| ロボット介護の導入など |
300億円 |
| 小規模保育支援など待機児童対策 |
200億円 |
| 企業・雇用 |
中小企業向けものづくり補助金 |
1600億円 |
| 女性、若者の雇用促進 |
1400億円 |
【軽減税率導入】
自民、公明両党は食料品など生活必需品の消費税率を低く抑える措置である軽減税率について「消費税率10%時」に導入することで折り合うこととなった。自公両党は消費増税に伴う低所得層対策として導入する方向で一致している。与党税制協議会の下に「軽減税率制度調査委員会」を設置し、対象品目、軽減する税率、財源、価格と税額を明記した送り状の整備、中小事業者の事務負担などを検討するとしている。